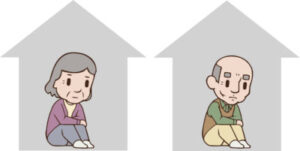自宅を持たない高齢者の住宅確保
年金生活の高齢者が賃貸住宅に住む場合は、家賃が家計費の大きな割合を占める。しかも、今後、配偶者の死亡に伴う年金の減額、建物の建て替えによる転居、入院、老人ホーム入所などの変化がありうる。年金額が少ない場合などは、早めに公的な高齢者向け住宅への入居を準備する必要がある。
高齢になってから、転居を迫られる可能性がある
人生100年時代という言葉のとおり、実感としては、統計的な平均寿命以上に長寿命化が進んでいる。もちろん、短命の人もいるが、長生きをした場合には、少なくとも配偶者の片方は90歳前後までは健在という状態になることは珍しくない。無職になった後も、概ね30年間程度は、どこかに自宅を維持しておかなければならないことになる。
ところが、自宅が賃貸住宅の場合には、今後、30年もの間には、建て替え、大規模改修、家主の相続による売却などにより、退去せざるを得ない可能性がある。また、賃貸住宅である以上、契約の更新期間に併せて、家主のさまざまな都合・事情により、退去を迫られる可能性がある。その結果、たとえば、「80歳代の単身高齢者が新居を探さなくてはならない」という事態も生じる。
こうしたことから、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」により、高齢者が、終身、安心して住めるような対策が施されていることになっている。「高齢者向けの賃貸住宅」、「シニア賃貸」などと検索すれば、高齢者歓迎という物件は数多くあることになっている。
しかし、実際には、高齢者(特に、単身者、心身が十分な状態でない人)の入居は敬遠される傾向にあるという。事故や孤独死のリスク、収入が無いといった懸念で、入居を断られたり、契約更新を拒否されることがあり、実際には高齢者の新たな借家探しは難しいと言われている。高齢者だけの家庭では、転居先を探すこと、転居費用を確保することも難しい場合が多いだろう。
うまく、転居先が見つかった場合でも、引越作業や事務手続きの負担、家賃の上昇、友人・知人など地域コミュニティの崩壊、見知らぬ土地での不便さといった事態が起こりうる。転居は、若い世代には何でもないことかもしれないが、高齢者のみ世帯にとっては、かなり、厳しいことが想定される。
家賃を払い続けることが難しくなる場合もある
また、余生の30年間程度、良い賃貸住宅に住み続けられたとしても、年金収入のみの生活の中で、自分の側の問題で、家賃を払い続けることが難しい経済状態になる可能性もある。
配偶者の死亡に伴う年金の減額
たとえば、夫と死別して、高齢の妻が85歳で「高齢者単独世帯」になったとき、夫の年金からの収入は無くなる。代わりに遺族年金を受給する場合でも、家計としての年金収入総額は大きく減ってしまう。
減額された年金収入だけで、今までどおり、光熱費、食費、医療費等の他に、そのころには値上がりしているであろう毎月の家賃をキチンと払い続けながら、生活費を工面できるかどうかは、分からない。
老人ホーム等との2重生活
また、夫婦とも健在であっても、「高齢者夫婦のみの世帯で、一方の配偶者が老人ホーム等に入所した場合」や「長期入院した場合」も同じだ。
「賃貸住宅での家賃などの生活費」と「老人ホーム費用又は入院費用」を2重に負担することになる。今までの、自宅での生活だけでも年金では足りないのに、その上、新たに、一方の配偶者の老人ホーム費用(または、入院費用)まで捻出するとなれば、年金で賄えるはずはない。夫婦が、いわゆる2重生活となり、大変なことになる。
病院と老人ホームの3重生活
さらに、この状態の中で、「配偶者の一方が、一定期間、入院・通院する場合」がある。その期間中は、「賃貸住宅での家賃などの生活費」と、「老人ホーム費用」、「入院・通院費用」を3重に負担する必要がある。年金額や老後資金が乏しい場合は、3重の費用をまかなうことは大変なことだ。夫婦とも同時期に入院した場合には、4重の負担になる。
個人差はあるが、高齢者は病気やケガが多い。「老人ホーム入居中でも、持病や転倒などによる一時的な入院・通院」がある。入院したからといって、安易に老人ホームを転出してしまうと、退院する先が無くなり、困ってしまう。この3重苦の期間は、意外に何度もある。
公的な賃貸住宅への入居を目指そう
高齢者向けや低所得者向けの県営住宅・市営住宅等
預貯金などが少なく、「年金以外の収入がないのに、年金額が少ない(低所得)」という状態であれば、それほど高齢にならないうちに、「生涯、住めるような公共機関による低所得向けの賃貸住宅」への入居を目指すことが選択肢の一つだ。
たとえば、「高齢者でも、年収などの条件に適合すれば、安く入居できる」という公的な賃貸住宅は各地にある。高齢者向けや低所得者向けの都道府県営住宅、市町村営住宅、高齢者向け地域優良賃貸住宅などだ。
当然、所得制限や現住所などの条件があるし、倍率もあるので、すぐに入居できるわけではないだろうが、通常の家賃が負担だと感じている場合は、有力な選択肢になる。
あきらめずに、都道府県の住宅供給公社や各市区町村役場の住宅担当などに、高齢者向け住宅、低所得者向け住宅の有無、申込方法等について問い合わせてみる価値がある。
その他、民間等の高齢者向け賃貸住宅
その他、民間企業や団体でも、各種の「高齢者向け賃貸住宅」などがあるが、概ね、高額だと思われる。内容的には、高級ホテルのような入口受付のある「ケア付き高齢者向け高級マンション」のようなものもあるが、生活保護受給者のみを対象にした簡易宿泊所のような所、グループホームのような所、公的施設のような名称の民間施設など、ピンキリのようだ。ただし、費用負担の問題の他に、さまざまな課題も指摘されている施設もあり、良く調査・相談してから入居する必要がある。
なお、通常の有料老人ホームも、制度的には老人が家賃を払って部屋を借りる下宿人スタイルだ。民間のサービス付き高齢者向け住宅等々の施設についても、有料老人ホームと何が違うのか、差異をよく調べる必要がある。
本当に困ったら、民生委員や市区町村に相談しよう
運よく高齢者向けや低所得者向けの公共的な賃貸住宅に入居できたとしても、家賃は無料ではない。入居後の、生活費の問題、入院費用、老人ホームに入る費用などの問題が解決したわけでもない。
高齢で働けない年齢・状況で、生活費や医療費等で本当に生活に困った場合は、公的な賃貸住宅への入居の有無にかかわらず、早めに、民生委員や市区町村の福祉担当に、生活保護などの相談をしたらどうか。
<広告>
今の自宅に、あと何年住めるのか
最近は90代の高齢者も珍しくないが、若い世代との同居は極めて減少している。自宅を持っている人でも、耐久性の面から、現在の自宅に、あと30年、100歳まで住み続けられる…
老後移住(1)田舎への移住は慎重に
「老後移住」という言葉が流行語のようになっている。しかし、そもそも、本当に老後移住をする必要があるのか。移住するとしても、どこに移住するかは、慎重に検討する必…